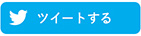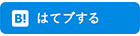各種世論調査で高市内閣の支持率は約7割と高い支持率を維持しています。この数字は石破内閣の支持率の約3割を大きく上回るものです。この高い支持率は、第1次安倍内閣を超えて歴代5位の高さとなっています。特に若年層や男性からの支持が伸びており、全体を押し上げています。
その人気の秘密は、彼女の「働いて×5」発言や、トップダウン手法による政策決定、ガソリン税の暫定税率廃止や所得税の控除拡大の実現などが寄与しています。一方で、積極財政に伴う日本国債の信頼性低下への不安、円安傾向の継続による物価高の加速と賃金上昇が追いつかない構図の悪化、利上げによる住宅ローン金利上昇などによる家計圧迫などが今後の足かせになると言われています。
また、政治の右傾化が加速していることも懸念材料です。自民党の連立相手が公明党から日本維新の会になりました。日本維新の会は、公明党より右寄りであり、ブレーキ役というよりも、アクセル役に回っています。
高い世論調査で言えば、消費税減税です。近時の物価高のなか、約7割の国民が支持しています。昨年の参院選挙では、自民党以外の政党が公約に掲げました。与党になった日本維新の会は先の参院選で、食料品を2年間ゼロ税率にすると言うことを公約に掲げていました。
同党の吉村代表は最近の発言で、物価高対策として食料品にかかる8%の消費税を「ゼロにするべきだ」と述べました。高市首相も以前は「国の品格として食料品の消費税は0%にすべきだ」と明言していました。
夫婦が同じ名字にするか別々にするか、自由に選べるようにする「選択的夫婦別姓」については、賛成が約6割を超えています。年代別では18~29歳で賛成が約8割となっています。日本弁護士連合会の調査では、95カ国で「夫婦別姓」が法制度化されていて、特に中国や台湾、韓国、北朝鮮などのアジア各国では、原則的に「夫婦別姓」で同姓を選べない法制度となっています。
婚姻しても婚姻前の氏を保持することを認めるという方向性は、世界共通の流れになっています。ところが日本は、これまで国連から選択的別姓制度を導入するよう4回にわたり勧告を受けていますが、いまだ実現されていません。
天皇の皇位継承などを定めている皇室典範を改正して、女性の天皇を認めることに、約8割の人が賛成しています。多くの国民は天皇、皇后の一人娘の愛子さんに敬意を抱いています。しかし、これまでの皇位継承のルールではただ「女性だから」というだけの理由で、天皇になる可能性があらかじめ除外されています。
皇位継承が男系男子と定められたのは、明治時代です。それまでは8人の女性天皇がいました。時代錯誤としか思えないルールです。急がないと、愛子さんが結婚したら現行制度では皇室を離れることになります。
物価高対策として有効な消費税減税の実施、男女の尊厳を取り戻すための選択的夫婦別姓の創設、時代錯誤の皇室典範の改正、いずれも高い国民の支持があります。
高い支持率の高市政権だからこそ、旧態依然とした自民党の意向に盲目的に従うのではなく、首相自らよく考えて、民意に沿った方向に大きく舵を切るべきです。