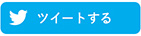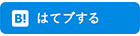2024年を振り返ると、自民党による企業・団体献金の「抜け穴」である政治資金パーティーを利用しての多額の裏金作りと、その後に発覚した総選挙における政党助成金2,000万円の「裏公認料」の支出が明らかになりました。
その結果10月27日に投・開票された総選挙では、自公連立政権が過半数割れをしました。この問題は、さらに追求して真相を明らかにしなければなりません。しかし政治は着実に民意で大きく変わろうとしています。
明るいニュースは、2024年のノーベル平和賞に、被爆者の立場から核兵器廃絶を訴えてきた日本被団協=日本原水爆被害者団体協議会が受賞されたことです。核兵器のない世界を実現するための努力と核兵器が二度と使用されてはならないことを証言によって示してきたことが受賞理由となっています。日本のノーベル平和賞受賞は、1974年の佐藤栄作元総理大臣以来、50年ぶりです。
ノーベル平和賞の授賞式が12月10日ノルウェーの首都オスロで行われ、メダルと賞状が授与されました。演説を行った代表委員の田中熙巳さんは「直ちに発射できる核弾頭が4,000発もある」「核のタブーが壊されようとしている」「人類が自滅することがないように、核兵器も戦争もない社会を求めてともに頑張りましょう」などと訴えました。さらに田中氏は原稿にはなかった「原爆で亡くなった死者に対する償いを、日本政府は全くしていないと言う事実をお知りいただきたい」との言葉を繰り返しました。
田中氏ら3人は、授賞式の翌日ノルウェーのストーレ首相と面会し、「日本政府が私たちの声に十分に耳を傾けているかと言えばそうではなく、日米同盟の中で核兵器禁止条約にすら署名も批准もしないという態度を持ち続けている。核戦争被害国と言っている日本が先頭に立たないといけないので、帰国後、政府に対してまず核兵器禁止条約を固めて、最終的には速やかに核兵器をなくすまで指導性を発揮するよう要請したい」と述べました。
いま、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が続き、プーチン大統領は核兵器の使用の可能性をちらつかせて威嚇しています。国連のグテーレス事務総長は「かつては考えられなかった核兵器を使った紛争がいまや起こりうる状況だ」と強い危機感を示しました。
こうした流れを食い止めることこそ、唯一の被爆国である日本の役割であり責任でもあります。たとえアメリカの核の傘の下にあってもそれは変わりません。政府は核兵器禁止条約の締結国会議へのオブザーバー参加を含め、より積極的で実効的な一歩を踏み出すべきでしょう。核兵器廃絶は待ったなしの課題です。
ところが、現在のところ石破茂首相に、唯一の被爆国の首相として、核廃絶への責任を担う意思がうかがえないことは甚だ残念です。
一方で世論調査会では、核兵器禁止条約に日本が「参加するべきだ」とした人が6割を超えています。今、政治の力関係が大きく変わりつつあります。ノーベル平和賞の受賞を力に、さらに世論を喚起して、核なき世界、戦争なき世界の実現のために、思想や信条を乗り越えて、日本が果たすべき役割を実行に移す年に2025年がなればと切に願っています。