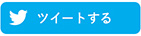12月10日に自民、公明両党は2022年度の税制改正大綱を決めました。閣議決定されたこの大綱をもとに、国税の改正法案については財務省が、地方税の改正法案については総務省がそれぞれ作成し、来年1月招集の通常国会に提出されます。現在の国会の力関係ではこの改正法案が年度内(3月末)に可決、成立します。
この大綱の目玉は、「成長と分配の好循環」を掲げる岸田政権のもと、企業の賃上げに対する税の優遇措置のさらなる拡充が盛り込まれました。減税規模は1,000億円と見込まれています。
具体的には、全体の給与総額をベースにみた賃上げ率などに応じ、大企業は最大で30%(現行は最大で20%)、中小企業は最大で40%(現行は最大で25%)の税額控除を行うというものです。
果たして、賃上げ促進税制の効果はあるのかはなはだ疑問です。そもそも賃上げは税制の優遇策で決まるものではありません。それは、労使の交渉などによって決まるものです。現にこの制度は13年度の導入以来、見直しがされて継続してきましたが、13年度に比べ20年度の実質賃金は、非正規社員の増加などが要因で低下しているとの指摘があります。
また、中小企業では赤字申告が約60%を占め、黒字申告をした企業でも納税額はわずかなところがほとんどです。こうした企業はその恩恵は受けられません。つまり、賃上げする体力がないと言うことです。中小企業の割合は99.3%で、そこで雇用されている従業員は全労働者の約7割を占めています。政府が取り組まなければならないのは、赤字企業などに対する支援です。例えば、社会保険料の負担割合を軽減するなどの措置が考えられます。
岸田首相が総裁選挙で掲げていた金融所得課税の見直しには、株式市場の急落などの要因で、やはり次年度に先送りとなりました。
欧米などは風力発電や太陽光発電になどに対する投資を促進する税制が進んでいますが、それに対しても何の言及もありません。また、温暖化ガスの排出量に応じて課税をする炭素税にも言及がありませんでした。
日本経済新聞の12月11日号で、矢嶋康次・ニッセイ基礎研究所チーフエコノミストがこの大綱について的を射たコメントをされているので紹介をします。『中長期の税の在り方がまったく見えなかった。法人税の引き下げと消費税の引き上げをセットで進めてきた流れが世界的に転換するなか、新しい税体系をどう考えるのか。カーボンニュートラルも骨太の論議から逃げた。
賃上げ税制は2013年から導入して効果がなかったものを多少変えたところで劇的には変わらない。賃上げに対応できるのは大企業だけで、赤字の多い中小企業との格差が開く皮肉な結果になるだろう。労働市場の改革をしないと持続的な賃上げは無理なのに、この10年ほど政治が議論から逃げている。
政府の税制調査会が中長期の税の在り方について論議をしないことも問題だ。』