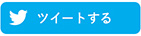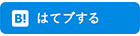教員のなり手不足に対応して、山口県教育委員会は、教員の採用試験を全国で最も早い時期に前倒ししましたが、志願者数は953人と前年と比べて79人減って過去最少となったと公表しました。同委員会は、民間企業の採用の前に教員の採用試験を前倒しするよう求めた文部科学省の要請に応じて、1次試験を前の年よりも2か月ほど早めて5月10日、11日の2日間実施しました。しかし志願者は初めて1,000人を割り込み、記録が残る1987年度以降、最も少なくなりました。採用人数はほぼ変わらない見通しのため、志願倍率は、前の年と比べて0.2ポイント低い2.3倍となりました。
教員のなり手不足は深刻な状況が続いていて、昨年度の全国の公立学校の教員の採用倍率は3.2倍と、3年連続で過去最低となりました。これを受けて、文部科学省は今年の試験の日程を民間企業の採用面接が始まる前の5月11日を目安に行うよう要請しましたが、それに応じた自治体はわずかで6県と3政令指定都市にとどまりました。そのうち志願者が増えたのはわずか3県だけで、文部科学省の思惑通りにはいかない実態が垣間見られます。
教員のなり手不足の理由について、あるアンケート調査では「長時間労働など過酷な労働環境」と94%が回答、次に、「部活顧問など本業以外の業務が多い」が77%、「待遇(給料)が良くない」が67%と続きました。深刻な実態が浮き彫りになっています。
このような状況の中、公立学校教員の給与などを定めた教員給与特措法が5月15日に衆議院で可決されました。この法案は、公立学校教員に残業代の代わりに基本給の4%相当を支給する「教職調整額」を2026年1月から毎年1%ずつ引き上げ、31年1月に10%とするのが柱です。その他に学級担任への手当を加算し、新たな職位として若手のサポートなどを担う「主務教諭」を設けることも盛り込まれています。
また、付則では、教員の時間外勤務を29年度までに月平均30時間程度に減らすことを目標に掲げ、1人当たりの担当授業時間数削減などを明記しました。さらに仕事を自宅に持ち帰る教員の状況把握、過労死が疑われる事案があった場合の迅速な調査・再発の防止なども付帯決議とされました。
私が幼い頃は、学校の教員には憧れの職業のひとつでした。その当時は、教員にはゆとりがあったような記憶があります。夏休みなどの長期の休みには教員も休みだったように思います。その上、奨学金を借りた人が教員職などに一定期間ついた場合には、返済を減免される制度もありました。しかしその制度は、公平性などを理由に教員については1998年4月入学者から廃止されました。
教育が社会の根幹を支える重要な要素であることは、誰もが認める事実です。しかし、現代社会ではその概念が変化し、より多様な価値観やスキルが求められています。知識の詰め込み教育から、創造性や批判的思考能力を育む教育へのシフトが必要です。少子化や国際競争力強化の中で求められるスキルは、問題解決能力やコミュニケーション能力です。
それを支えるのは、質の高い教員であることは異論がありません。そのためには、現場の教員の「働きやすさ」と「働きがい」をどう両立させるかが大きな課題だと考えます。